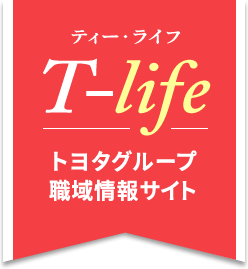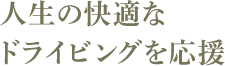損害保険を契約する際に必ず支払う保険料、毎年継続している自動車保険でもお車を買い替えたりすると保険料が高くなったり、安くなったりします。
そんな保険料はどんなふうに決まっているのか、また、いざ事故が起きた際の保険金の請求と支払いについて今回はご説明していきます。
保険料の決まり方
保険料は大まかにいうと、「保険金額」「加入者数」「発生率」を基に計算されます。
例えば保険金額が100万円、加入者が1万人、保険金支払事由の発生率が0.5%の保険があったとします。
加入者1万人に対し発生率0.5%ですから、50人に対し支払いが生じることになります。
50人に100万円支払うわけですから、保険金は総額5,000万円必要になります。
この5,000万円を加入者全員で負担すれば1人あたり5,000円。
したがって、保険料は5,000円という考え方です。
実際には、その保険を運営するための経費等やさらにたくさんの過去のデータを加味して決められます。計算をする際には、次の3つの考え方で適正な金額を導きだします。
《大数の法則》
事故の発生確率を出す時には、数件の事故ではなく、多くの事故データを分析します。より多くのデータを分析すればする程、正しい発生確率を予測できるようになります。
例えば、サイコロを振った時に1から6までのそれぞれの数字が出る確率は数回振っただけでは一定しませんが、1,000回、2,000回と繰り返すと、それぞれの数字が出る確率は6分の1に近づいてきます。
この発生率の法則のことを「大数の法則」とよんでいます。
《公平の原則》
事故の確率が高い人には高い保険料を、低い人には低い保険料を設定し、皆が平等になるようにしているのが「公平の原則」です。
例えば、走行距離が長い人と短い人では走行距離が長い人程、事故にあう確立は高くなるので保険料は高くなりますし、スピードが出るスポーツカーと軽自動車では、スピードがでるスポーツカーの方が事故がおこりやすいので保険料が高くなります。
また木造住宅の方がコンクリート住宅よりも火事で燃えやすいので、保険料は高くなります。
《収支相等の原則》
保険契約者の皆様から集めた保険料(収入)と、保険会社が支払う保険金と経費(支出)の総額が等しくなるように計算します。これを「収支相等の原則」といいます。
経費の中には代理店の手数料や保険会社の利益も含まれています。
保険金の請求と支払い
①事故がおきたら、警察・消防への連絡(契約者)
交通事故や盗難、火災などの事故が発生した場合には、警察署や消防署などへの事故の届出を行ってください。保険金の請求には原則として、警察等が発行する事故の証明書が必要となります。(当然、けが人の救護等は最優先で行ってください。)
②保険会社や代理店に事故の連絡(契約者)
警察等への届けの後、契約先の保険会社や代理店に連絡してください。
最近はほとんどの保険会社が24時間365日、コールセンター等で事故の対応をしています。あらかじめ携帯電話に電話番号を登録しておくと、いざという時に、あわてずに済みます。
物損事故、人身事故共、事故現場で、相手方にいくら支払う等の約束(示談)は絶対にしないでください。相手の氏名、連絡先、車両番号等確認して、相手方との交渉は保険会社にまかせるようにしてください。
③必要書類の提出(契約者)
事故の種類や内容に応じて、保険会社から必要な書類の案内が来ます。
指示に従って提出します。
④事故の調査と保険金額の査定(保険会社)
保険会社では事故の調査を行い、保険金を査定します。
自動車保険や火災保険については定額の保険金支払いではなく、事故の状態や程度によって支払われる保険金が変わってきます。
また、実際にうけた損害に対してのみ支払いがおこなわれる実損払い方式の為、例えば家が火災に遭い、ついでに建て増しを行った場合その費用は支払われません。(事故の直前よりも良い状態にする費用は支払われません。)
契約内容によってはその金額以下の損害については保険金が支払われない免責金額が定められていたり、自動車事故においてはそれぞれの過失割合(それぞれの落ち度の割合例 60:40 70:30 等)によって保険金額が変わってきますのでご注意してください。
⑤確定した保険金の支払い(保険会社)
査定理由を説明したり、相手方との示談を締結したうえで、保険金が契約者や相手方が指定された振込み先に支払われます。
次回からは生命保険について解説しますのでお楽しみに!
 一覧に戻る
一覧に戻る