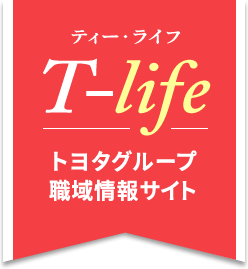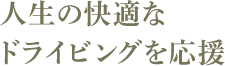皆さんの生活の身近なところにある保険。
今や、保険に全く加入していないという方はいないのではないでしょうか。
保険には多くの種類があり、ひとつひとつをしっかり理解しているという方も少ないように思われます。
例えば、自転車で人にぶつかり、けがをさせてしまった。こんな場合、保険でカバーできるのか、もしできるのであればどんな保険でカバーしたら良いのか。
自動車の事故ならすぐ分かるでしょうが、自転車の場合すぐに答えることのできる人はなかなかいないでしょう。
色々な保険の内容を理解し、必要な際に必要な保険を使えることができるよう、また、重複して保険をかける事などがないように、まずは「保険」と呼ばれるものにはどんな種類があるのか、その種類からみていきたいと思います。
保険の種類
■第1分野
人の生存または死亡に関し、一定の保険金を支払う事を約する保険
所謂、生命保険の分野にあたります。
■第2分野
一定の偶然な事故によって生ずることのある損害を填補する事を約する保険
所謂、損害保険の分野にあたります。
■第3分野
身体の傷害、疾病および介護に関し、一定額の保険金を支払うこと、または損害を填補する事を約束する保険
生命保険、損害保険いずれにもあてはまらない保険ですが2001年から生命保険・損害保険双方の保険会社で取扱えるようになりました。
第1回はこの中の「第2分野 損害保険」について、その始まりや特徴の説明をしていきたいと思います。
損害保険の始まり
■損害保険の始まりは海の上
古代ギリシャ時代の海上輸送では嵐など予期せぬ危険に遭遇した場合、荷主と船主で積荷等の損害を負担するという習慣が生まれました。これが損害保険の考え方の始まりです。その後、14世紀になると航海が失敗した時は金融業者が積荷の代金を支払い、航海が成功したときには金融業者に手数料を支払うという仕組みをイタリアの商人たちが考え出し、それが「海上保険」に発展しました。
■ロンドン大火
1666年9月のロンドン大火は4日間にわたって燃え続け、ロンドン市内の約85%が焼失するというほど大規模なものでした。この火災を契機に海上保険をヒントに考案された火災保険が登場しました。過去の火災発生率と現在の建物数から保険料を設定したりするなど近代的な火災保険の原型となるものでした。
■日本の損害保険の歴史
日本の損害保険の歴史も海上輸送から始まりました。16世紀から17世紀の初めに活躍した朱印船には「なげ金」という制度が考え出されました。金融業者が証文に基づいて金を貸し、無事に航海が終われば、利子と元金を徴収、船が難破した場合は何も払わなくていいというものでこれが日本における損害保険の原型です。
日本人自身による最初の損害保険業は1869年に神奈川県の税関が日本人による初の保険を実施。やがて多くの保険会社が誕生していきます。
損害保険の特徴
損害保険とは「保険会社が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約するもの」保険法では損害保険契約についてこう記しています。
偶然の事故とは例えば、台風・火災・地震・傷害・盗難があげられます。つまり、偶然のリスクによって保険の対象に生じた損害をカバーする保険、それが損害保険です。
保険金についても自由に設定することはできず、保険の対象となる「モノ」の値段や価値に合わせて設定します。
また、実際に事故が起きた時に支払う保険金については、例えば、交通事故をおこしたらいくらではなく、実際に交通事故で発生した実際の損害額を払う実損払い方式を取っています。
 一覧に戻る
一覧に戻る