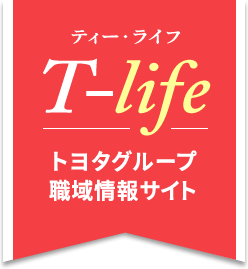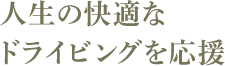購入するマイホームが具体的になってきますと、家族の夢も大きく膨らんできます。
そろそろ住宅ローンの借入れをする金融機関をどこにするか考えねばなりません!
一般的に金融機関を選ぶ際、以下のケースが多いようです。
・給与振込みのある金融機関(我が家のメインバンク)
・職場で提携ローンのある金融機関
・不動産会社が提携している金融機関
・近所にある金融機関 など
その中で、次の2つのポイントでどの金融機関からどんな住宅ローンで借入れするか選んで頂くと良いですよ!
①住宅ローンのタイプ(適用金利について)
②団体信用生命保険の保障内容等
最終的な決め手は、最長35年の超長期の取引をする金融機関を選ぶのですから、親身なって相談できる、安心して取引のできる金融機関と取引したいですね!
住宅ローンのタイプ(適用金利について)
しかし金利が低いローンは、返済中に金利や返済額が上がる可能性があることに注意!住宅ローンは金利だけでなく、返済中に金利がどう変わるか「金利タイプ」も見極めて選ぶことが大切となります。
【低金利のメリットとデメリット】
金利の低い住宅ローンは、同じ返済額で多額の借り入れができます。しかし、その多くが「変動型」や「固定期間選択型」など、返済中に金利が変わるタイプです。将来金利が上がったら返済額も増えてしまいます。一方、「全期間固定型」のように、金利は高めだが返済終了まで金利が固定されるタイプもあります。
【変動型を選ぶときの注意点】
変動型を選んで金利が上がる場合、5年後の返済額アップは前回の1.25倍が限度。つまり、毎月返済額が10万円なら、次は最高12万5000円になる可能性があります。現在の金融状況では、数年内に金利が急に上がる事態は考えにくいですが、住宅ローン返済は最長35年と長期にわたります、どちらが有利かは判断が難しいところです。10年、20年後の家計も考えて選択しましょう。
「全期間固定型」は、借入時の金利を返済終了まで固定するタイプです。変動型などに比べると金利は高めとなりますが、返済中に金利や返済額が変わらないという安心感がメリットです。返済額が一定ですので将来プランも立てやすく、マイホームを買った後は、子どもの教育費の貯蓄などに集中できます。良く耳にされると思いますが、「フラット35」というローンが代表的です。金利は金融機関によって異なるので、比較して選ぶようにしましょう!
「固定期間選択型」は、2年、5年、10年、20年など、金利が固定される期間を選べるタイプです。固定期間中は金利も返済額も変わらず、期間終了後はその時点の金利を見て、改めて固定期間を選べる点がメリットです(※)。金利は固定期間ごとに決められ、期間が長いものほど高くなります。また、選べる固定期間は金融機関によって異なります。
※期間終了後、固定期間選択型と変動型のいずれかを選択できる商品も多い
■さらに調べて「金利引き下げサービス」の内容をチェックしよう!
「金利引き下げサービス」とは、金融機関との取引条件を満たす人に対して、店頭金利よりも低い優遇金利を適用するサービスです。これを使わない手はありません!是非、ご活用を!
団体信用生命保険について
民間金融機関の多くは、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件です。この場合には、保険料は金利に含まれており、別途に保険料支払いは発生しません。ただし、健康状態が良好で、生命保険に加入できる状態ではないと団信付住宅ローンも借入れできないということになります。当初借入時のみならず、借換えの際も同様となるので、健康でいることは、より良い住宅ローンを借入れするためにも必要なことです。
金融機関によっては、通常の団信の保障に加えて、三大疾病保障付き、七大疾病保障付きなど、特約付きの団信も数多く出ています。例えば、三大疾病保障は、「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」についての保障になります。ただし、所定の状態になったらすぐに保険金が支払われ、住宅ローンの残高が清算されるもの、一定期間は毎月の支払額が支払われ、その状態が続いた場合にローン残高が清算されるものなど、支払われ方が異なるので確認してみましょう。
保険料についても、保険料は銀行負担のもの、金利0.3%程度の上乗せのもの、月額で支払うものなど、金融機関によって様々です。
もし、本人が死亡してしまった場合、ご家族の方は直ちに住宅ローンを借入れている銀行に直ぐに連絡してください。連絡が遅れてしまうと、返済が滞納している時などは一部の利息が支払われない場合もありますので注意!
減額となった保険料を住宅ローンの繰上返済資金に充当したり、良い資金運用プランを検討することも賢いやり方です。
既に住宅ローンをお借入れの方も一度自分の保険の確認されることをお勧めします!
 一覧に戻る
一覧に戻る