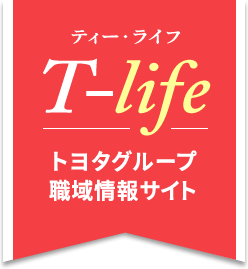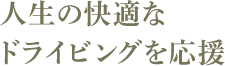先日、仕事でいなべ(三重県)に行った際、道端に立つ「梅まつり(いなべ市梅林公園)」の宣伝ののぼりを目にし、さっそく休日を利用して行ってきました。
きれいな梅

公園には、満開の休日ということもあって、たくさんの方々が来場し、春の到来を楽しんでいらっしゃいました。ここ、梅林公園は東海地方最大級の梅苑とのことで、広さはなんと東京ドーム8個分の38haもあるそうです。そして梅の木は100種類、4,500本もあるのだそうです。
梅の木ってたくさん種類があるのですね。
梅の種類について、ちょっとインターネットで調べてみました。
梅の種類
梅は花の観賞を目的とする「花梅(はなうめ)」と、実の採取を目的とする「実梅(みうめ)」の大きく2つ分けられ、「花梅」は更に「3系」に分類されるそうです。
【花梅の3系】
(1)野梅系
原種に近い梅で中国から渡来した梅の子孫と言われるもので、花は白又は淡紅が多く香りが高く果実は丸い。
(2)緋梅系
野梅系から変化したもので、花は紅色・緋色のものがほとんど。
(3)豊後系
梅と杏との雑種。杏に近く、花は桃色のものが多い。

【実梅】
加工して梅干や梅酒になる「実梅」も、梅干で有名な「南高」などいくつかの種類があります。梅の実を生で食べることはありませんが、「梅は三毒(食べ物の毒・水の毒・血の毒)を断つ」といわれるほど、昔からその効能がよく知られています。
梅のすっぱさのもとであるクエン酸には、体内でのエネルギー代謝を活発にして疲労物質の分解を促進するはたらきなどがあるそうです。これからはおにぎりの具は梅干、晩酌は梅酒ソーダ、これで体調もばっちりですね。
梅の名所
東海地方にはまだこれからでも間に合う梅の名所もありますのでご紹介しておきます。いずれも4月中旬位までは見ごろのようです。
①飛騨天満宮(岐阜県高山市)
平成14年に大宰府天満宮から菅原道真が愛した梅木が神納される
②古子の紅梅(岐阜県下呂市)
県の指定天然記念物の樹齢700年とも言われる1本
今週末でいなべの梅のみごろは終わってしまいますが、6月には「梅の実もぎ取り」のイベントもあるようなので、興味がある方は参加されて自家製の梅干・梅酒作りに挑戦してみても良いかもしれませんね。
 一覧に戻る
一覧に戻る